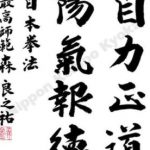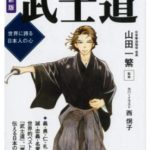防具について
防具を装着して自由に撃ち合う。この中に技術の変化を学び、体力を練り気力を養う。そして個性に合った技法を体得する。ここに拳法の武道・格技スポーツとしての行き方がある。
防具は、人体のうち最も大切な箇所(急所)を加撃から守るために着用する面、胴、股当と攻撃手拳ならびに足を保護するグローブ、シューズから成り立っている。
防具を装着したとき、よく合っているかどうかは戦力に大きく影響する。面はよく顔に合い、グローブは握りやすく、突き指などすることのないように調節することが大切である。


防具について
防具はわれわれを鍛えてくれ、これによって競技ができる。考え方によれば生命の恩人である。大切に扱わなければ上達は望めない。

各防具の説明
1、面

2、胴

3、グローブ

4、股当
左右の紐を均等に後ろ縦帯に通し、交叉点を左手で持ち、左、右と両脚を両側に入れ、股間まで引き上げて締める。紐が下腹部を交叉するときは、できるだけ下から引き上げるように締め、紐の最後は背後で余りをなくし、しっかりと結こと。股当は練習時は下衣の上から着けるが、競技大会には下衣の下に着けるものとする。
5、シューズ
道場や競技場の床面に合わせて、スベリ止めの適正をはかることが大切である。
●防具の着脱
股当以外は坐るか、腰を掛けて行う。
●防具の置き方
胴を立て、その内側に股当、面、グローブの順に置く。
防具の手入法
防具は風通しの良い日陰でよく乾かすこと。特に面は汗を吸うと暖衝力がなくなるから危険である。グローブは詰め物の多少や片寄りが拳を痛める原因になるので、保革油を塗布し、型崩れがないようよく注意する。
階級章
有段者は黒帯の着用と、上衣の両そでに付けた黒線で示す。黒線は初段、二段は1本、線幅1.5cm~1.7cm。三段以上は2本、線幅1.0cm。ともに袖口より5cm離して縫い付ける。有段者は内規にて示す。
むすび、むすぶ
”結び”が身のまわりから急速に減ってきている。洋式生活になって和服もめったに着なくなった。荷物も紐て結ぶよりも、紙袋に入れて粘着テープでとめることで用が足りる。子供のズック靴も、ワンタッチではける面ファスナーが幅をきかせている。粘着技術の発達で、確かに生活は便利になったが一方で手先の器用さを奪ってしまう。拳法の防具は、紐で結ぶところが多い。子供のときから結ぶ機会が少なくなっているから、上手に着けられない。また、結び方が悪いから、すぐゆるんでくる。試合のときには、テープで留めているのを見かけるようになった。この点から、防具改良案も出るこの頃である。”むすぶ”の邦語は、群統である。相対したものを統一して、より一段高次な価値に進めることをいう。われわれが己を空して己を忘れ、己を擲って、偉大なる感激の対象に生きることが”むすび”である。手は脳の出張所という。子供たちが手先を使わなくなったこと。今から二、三代先はと心配する人もいる。